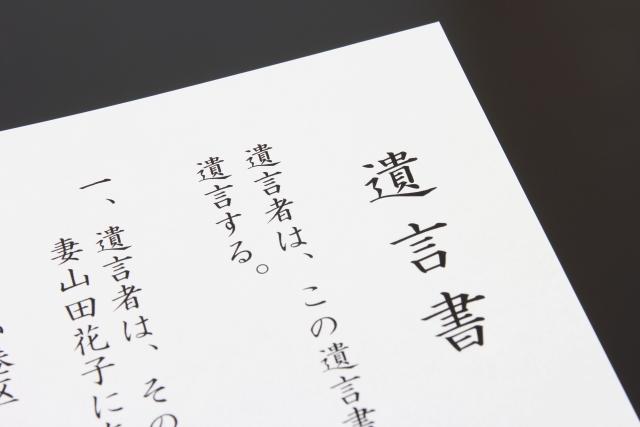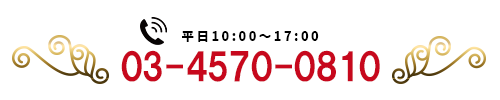03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
岸田康雄– Author –
公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。
-

不動産の取得と賃貸経営に係る税金を確認しておこう
不動産取得税 不動産取得税は不動産を取得した場合に、その不動産の所在地の都道府県が課す税金です。たとえば、土地や家屋を購入、家屋を建築して不動産を取得したときには、登記の有無にかかわらず課税されます。 ただし、相続により取得した場合、法人... -

土地の売却!譲渡所得を節税する方法を教えます!
複数の不動産を売却するなら、同じ年度中に売却するようにしましょう。利益が出る物件もあれば、損失が出る物件もあるでしょう。不動産の譲渡所得は、利益を損失で相殺することが可能です。同じ年に売却するだけで数百万円も節税できることもありますので... -

不動産売却の税金?土地の取得費がわからない場合の計算は?
相続した実家を売却する際に心配になるのが、いくら税金を取られ、手取りがいくらになるのかということです。しかし、親が土地をいくらで購入したかなど、記録に残っているはずがありません。取得費がわからない場合の対応策を説明します。 親から相続した... -

プライベートバンカーの仕事とは?高齢の富裕層に必要なサービスとは?
手数料を稼ぎまくる大手金融機関の問題 これまで、金融機関のリテール営業担当者は、金融商品を回転売買させて手数料を稼ぐことに注力してきました。為替手数料を稼ぐための外国債券、元本を取り崩して毎月高い分配金を支払っているかのように見せる投資信... -

宅建業者の両手取引では売主の利益が犠牲になる!
不動産売買に伴うコストはいくらか? 宅地建物取引業者(宅建業者)を介して不動産の売買を行った場合、所定の仲介手数料を支払わなければなりません。仲介手数料は、通常は売買契約成立時にその半額を、残代金支払い時に残りの半額を支払う方法が多く採ら... -

不動産の売却・購入は慎重に進めよう!売買手続きと不動産登記
不動産を「売却する」手続きは? 不動産の売買には、法律や税金、登記など様々な分野が関係するため、慎重に意思決定を行う必要があります。事前に様々な情報を入手しておかなければなりません。 いくらで売るか? 不動産を売りたい場合、売却価格をいくら... -

今でも有効なのか?事業用資産の買換え特例をわかりやすく解説!
賃貸している不動産を売却し、新たに賃貸用の不動産を購入すると、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができます。ただし、無条件で繰り延べることができるわけではなく、様々な条件があります。事業用資産の買換え特例を利用して、不動産経営に... -

【資産運用の基本】金融資産の目標利回りとリスク許容度はどのように設定すべきか?
資産運用の利回りを決める前に考えておくべきこと 老後2000万円問題など、公的年金だけに頼っていては不安な時代です。長期・積立・分散投資の必要性が認識されつつあります。 資産運用を始める際には、とにかく稼ぎたい!高い利回りを実現させるぞ!など... -

【資産運用の基本】投資対象の金融商品はこう選ぶ!
資産運用をする場合、そもそも不動産か金融商品かの選択があります。ここでは金融商品を選ぶとしましょう。どの金融商品に投資するかの選択が必要となります。ここでは主な金融商品の平均的な利回りやその特徴を見ておきましょう。 銀行預金 国内の銀行預... -

不動産投資と金融商品投資との比較、居住用・事業用どちらがいいか!
不動産という資産の特徴を理解しよう 不動産は投資対象の一つ 不動産は、自ら利用(住む、事業で使う)、保有することにより満足を得ることができるものです。つまり、自ら居住することもできますし、事業に使うこともできます。 自宅を所有するか賃貸にす... -

売却(M&A)の準備(2)~経営の磨き上げとは?
親族外承継(会社売却)を決めた場合、その企業は1円でも高く売却したいと思われる事でしょう。 親族内承継をするのであれば、株式に係る相続税を安くするために、会社の評価額を下げる必要がありますが、売却の場合は逆の発想になります。 ここでは売却額を... -

親族外事業承継(M&A)をついに決意!誰に相談すればよいか?
親族外承継(M&A)を相談すべき相手は税理士か公認会計士 事業承継は一生に一度の重大なイベントであり、それを失敗すると、これまで築き上げてきたすべての事業価値を失ってしまいます。それゆえ、事業承継を行う際には、専門家のアドバイスが不可欠... -

一般社団法人へどのように個人財産を移すのか?資金調達は?
一般社団法人の資金はどうやって集めるか? 一般社団法人は資本金が無いため、出資による資金の払込みを受けることができません。それゆえ、資金調達は、法人への寄付、法人の基金、借入金の3つの方法によることとなります。 普通法人である一般社団法人... -

一般社団法人を資産管理に活用する方法
富裕層の資産管理の手段として、一般社団法人に個人財産を所有させるケースがあります。一般社団法人は持分のない法人です。株式会社と異なり法人のオーナー(出資者)が存在していません。それゆえ、以前は、相続税対策の手段として使われることもありま... -

最高1,500万円の投資回収が確定する事業承継補助金とは?
事業承継補助金は親族内とM&Aの2タイプ 事業承継補助金は、平成29年度に始められた経済産業省の補助金です。この補助金は、事業承継をきっかけとして、経営革新や事業転換に取り組む中小企業者などを支援することが目的となっています。 過年度の事業... -

50億円のビルを相続?賃貸不動産の民事信託の活用事例
【事例】大規模な賃貸不動産を共有するには民事信託が有効! 【お悩み】 私は大規模な賃貸オフィスビルを所有しております。資産規模は50億円です。私の相続が発生した場合、3人の子供たちがこのビルを共有することになりそうです。それゆえ、将来的にビ... -

富裕層の資産管理に使える!一般財団法人と公益社団法人
社団法人と財団法人とは法人格の対象が異なる 社団法人とは、人の集まりのことをいいます。すなわち、社員の集まりに法人格が与えられたもの。基本的には運営費を構成員が負担して活動することが想定されています。 これに対して、財団法人とは、モノの集... -

100年経営研究機構 後藤俊夫代表理事×公認会計士 岸田康雄氏 対談 ~ファミリービジネスの事業承継に必要な「家族の対話」への支援~
日本の政府は、2025年までにM&Aによる親族外承継を含めた、事業承継の集中的な支援を行っていくことを発表しています。この点、親族内承継によるファミリービジネスの強さを研究しているのが、100年経営研究機構の代表理事である後藤俊夫氏です。 今回... -

【不動産M&A事例紹介】浅草の老舗料亭を不動産M&Aで売却
複数の親族が関与する会社は合意が困難 浅草の老舗料亭を経営するA社の2代目甲社長は、70歳になって、引退したいと考えていました。A社の浅草にある料亭は、甲社長の父親の代に開いた古い店舗です。 父親の代にその土地に10階建てのビルを建て、1階は... -

個別不動産ではなく、不動産を持つ会社を売買する!「不動産M&A」とは?
「不動産M&A」という手法を考えてみたい 銀座や赤坂などの一等地を見ると、歴史と伝統ある会社がたくさんあります。「百年企業」という宣伝もありますように、長く続いている老舗企業はとても立派に見えます。 しかし、その内情は、何度も相続を重ね、... -

実家の売却で3千万円まで税金ゼロ!「空き家特例」の使い方とは?
誰も住んでいない実家の売却で節税できる「空き家特例」とは 2023年12月31日までに、空き家となった実家を売却すると、譲渡所得(儲かった分)のうち3,000万円まで、課税されない特例があります。ただし、特例を適用をするためには要件がありますので、空... -

民事信託は遺言や成年後見よりも使いやすい!株式の信託と受益者連続型信託まで!
成年後見人制度よりも民事信託が優れている理由 成年後見人とは? 認知症など判断能力が低下した高齢者を支援する制度として、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がありますが、いずれも家庭裁判所の関与が不可欠です。 一般的な財産の管理や処分... -

民事信託を開始する方法は?会計と税務(所得税)はこれだけ!
民事信託を開始するにはどうするか? (1)信託契約の締結 信託の設定方法は3つあります。一つは、委託者と受託者との契約によって設定する方法です。すなわち、委託者と受託者が信託契約書を作成します。 この場合、受益者は契約の当事者にはなりません... -

親族外事業承継(M&A)で買い手候補を探し出す方法
M&Aの買い手候補を探し出す方法 買い手候補の情報を集めるには、以下の三つの方法があります。 ①売り手の経営者が自ら探し出す方法 ②M&Aアドバイザーに依頼する方法 ③金融機関から紹介を受ける方法 買い手候補探しを行うためには、情報力が必要で...