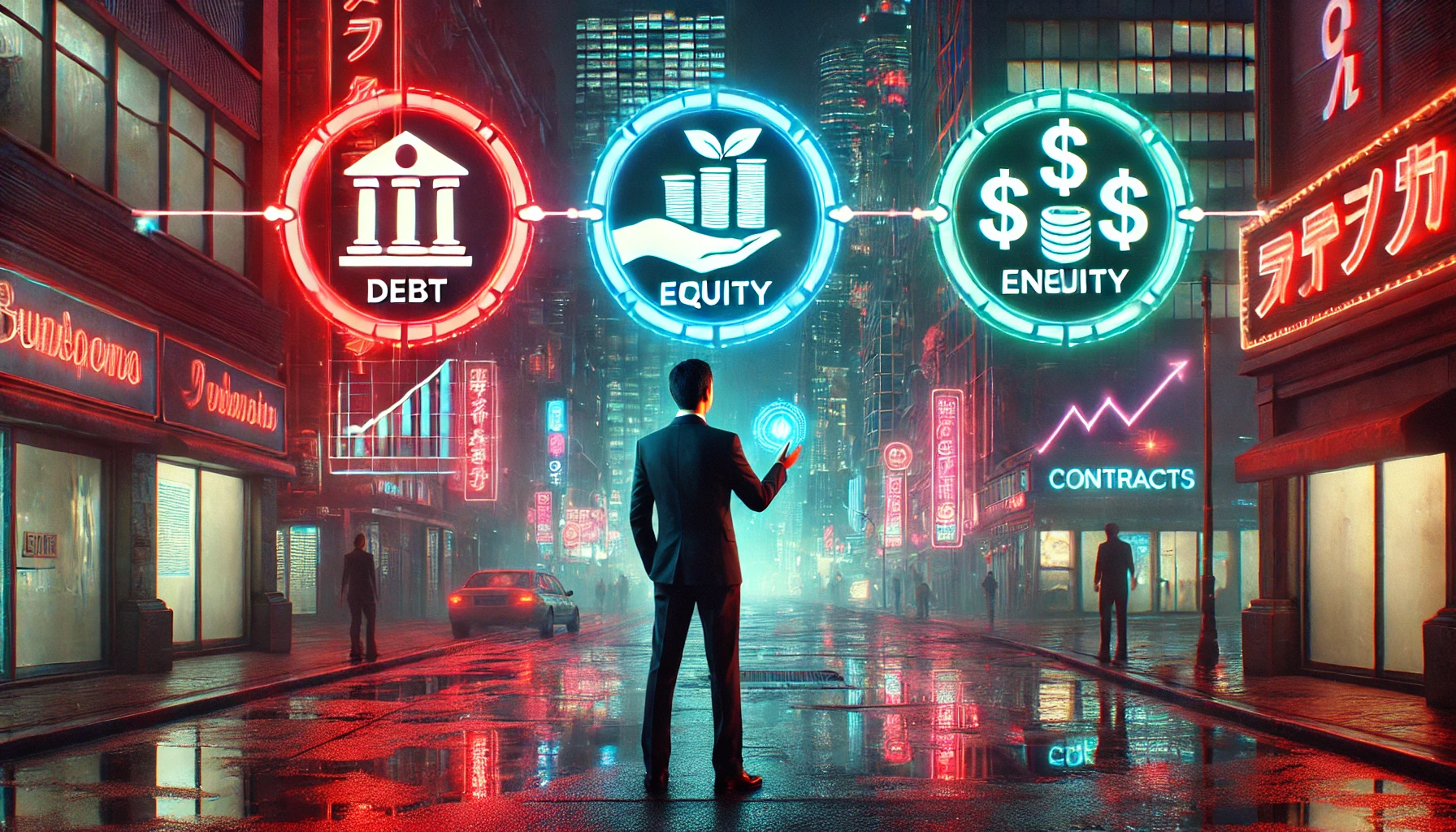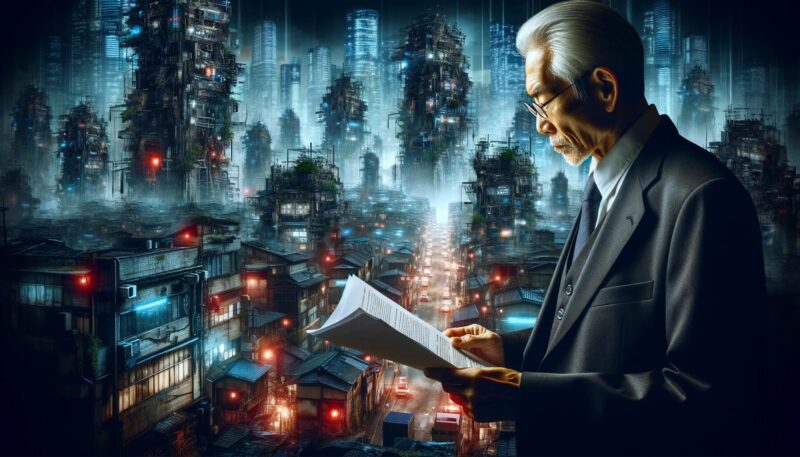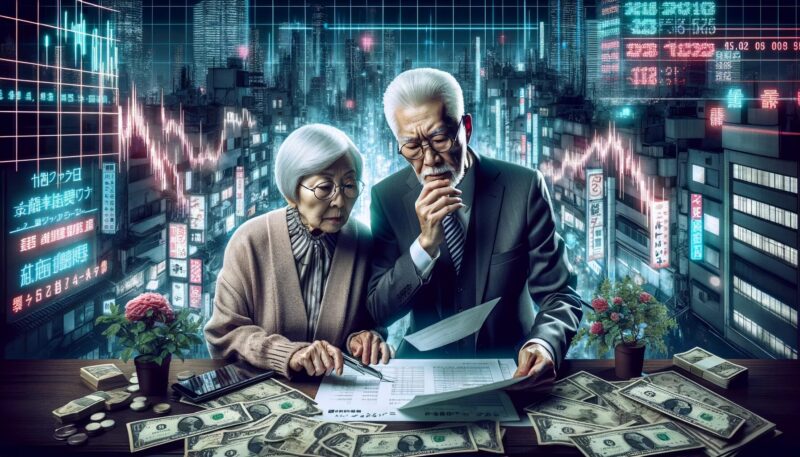0120-1000-77/03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
最新ニュース

【保存版】資金調達の基本と実践!融資との違いと成功する調達戦略とは?
資金調達の本質とは何か? 事業の立ち上げや拡大において、資金調達は欠かすことのできない生命線である。資金調達とは、企業や個人事業主が事業を進めるために必要な資金を外部から確保することを指す。これは単なる「お金集め」ではない。成長戦略を実現...
資金調達を正しく理解する:負債・資本・現金化それぞれのメリットとデメリット
資金調達方法の選び方で事業の未来が変わる 起業や事業拡大に際して避けて通れないのが資金調達である。多くの経営者にとって、どの資金調達手段を選ぶべきかという問題は、経営戦略そのものに直結する重要な意思決定である。 資金調達には大きく分けて、...
起業家必見!負債・出資・現金化・補助金まで、資金調達のすべてを徹底解説
事業立ち上げの壁は「資金」 新たに事業を始める際、多くの起業家が最初に直面する課題が資金調達である。とりわけ中小事業者やスタートアップにとって、自己資金だけで初期費用や運転資金を賄うのは難しい。調達手段には多様な選択肢があり、それぞれ資金...
ステージ別に見る資金調達の実践的手法~創業期・成長期・成熟期、それぞれの資金戦略とは
起業家や個人事業主にとって、資金調達は常に重要なテーマである。どれほど魅力的なビジネスモデルを描いていても、資金が不足すれば事業の継続や拡大は困難となる。しかし、資金調達の方法は、事業のフェーズによって大きく異なる。この記事では、創業期...
資金調達のプロセスを徹底解説
企業や個人事業主にとって、事業の立ち上げや拡大には資金の確保が欠かせない。資金調達は単なる財務手続きではなく、将来の成長を見据えた経営戦略の中核をなす。本稿では、資金調達の基本的な流れを体系的に整理し、各段階における実務上の留意点を提示...
【自社株対策】中小企業経営者の相続対策と事業承継の基本
自社株式は、会社の「経営権」を表すものであると同時に、企業経営者の「個人財産」です。現預金や不動産のように、子どもたちへ均等に分ければよいというものではありません。今回は、自社株式の相続について考えてみましょう。 自社株式の遺産分割は難し...
年金の基礎知識:中高年が知るべき老齢年金及び遺族年金の受給の要件
遺族基礎年金 自営業のご主人が亡くなったとき、奥様と未成年のお子様は、お子様が18歳になる年度末まで遺族基礎年金を受け取ることができます。 国民年金の第1号被保険者が亡くなったときのお金は3種類 自営業者などの第1号被保険者が亡くなった場合、遺...
【年金繰下げ受給】老後資金で大失敗!引退した中小企業経営者は注意せよ!
中小企業経営者の多くは、65歳を過ぎても働き続けています。年金受給開始も繰り下げされる方が多いでしょう。今回は、年金繰り下げ受給の注意点について解説します。 年金繰下げ受給とは何か 年金の繰り下げ受給とは、本来の年金受給開始年齢を遅らせるこ...
【遺族年金と死亡保険金の税務】経営者の夫が50代で急逝した!残された妻はどうする?
経営者として忙しく働いていた夫が脳梗塞や心筋梗塞で倒れ、突然他界してしまうことがあります。そのようなとき、残された奥様がどうすればよいか解説しましょう。 相続税の申告 相続によって奥様がご自宅を承継する場合、相続税負担が重すぎると、住み続...
事業承継と節税戦略:持株会社設立と「株特外し」の活用
事業承継は企業の存続と発展に直結する重要な課題です。この記事では、事業承継における株式承継に焦点を当て、持株会社設立や「株特外し」などについて解説します。 持株会社設立のメリット 事業承継には、先代経営者から後継者への株式の承継が伴います...
事業承継の方向性(親族内承継、従業員承継、第三者承継・M&A)と事業承継フレームワーク
経営者も人間(親)であるから、自分の子供に事業を継がせたいとするのが心情であろう。しかし、近年、子供が親の事業に興味を持たず、他分野でキャリア形成しようとすることから、親の後継者になろうとしないケースが増えている。 子供が承継しないことに...
ガソリンスタンド業界のM&Aとは?
ガソリンスタンドの事業承継とM&Aが増えてきました。ガソリンスタンド業界のM&Aについてご説明しましょう。 ガソリンスタンド業界の市場環境 ガソリンスタンド業は、計量器付きの給油ポンプを備え、自動車そのたの燃料用ガソリン、軽油および液化...
「賢い不動産売却で老後を安心に」50代60代の資産最大化戦略:相続・事業承継を見据えて
賃貸マンションを所有していて、空室率の増加や賃料収入の減少に頭を悩ませている方、また、終の棲家としての自宅の住み替えを検討される方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産の売却を考えるタイミングなどについて、わかりやすく解説いたします...
遺言書の基本的な書き方を解説!無効にならないためのポイントは?
近年、「終活」がブームのようになっています。人生の終わりを元気なうちに見据え、訪れる「死」に備えなければならないということを、コロナ禍を経験して、多くの人が切実に感じ始めているようです。 終活で遺言書や流行りの「エンディングノート」を作っ...
相続時における銀行預金の解約や名義変更について解説
亡くなった方が銀行口座を持っていた場合、相続人は速やかに銀行口座の解約や名義変更をしなければいけません。 銀行口座の解約や名義変更の手続きには、さまざまな書類が必要です。書類に不備があると、手続きがなかなか進まなかったり、何度も銀行へ足を...
M&Aによる事業承継:経営者は親族内・従業員・第三者の選択を行う
子どものキャリアを考える 経営者としての長いキャリアを経て、引退を考えるときが来ます。しかし、後継者が見つからないという問題に直面することがあります。 経営者も人間(親)であり、自分の子供に事業を継がせたいと考えるのは自然なことです。しか...
相続がとても簡単!法定相続情報証明制度の利用
相続手続きのために戸籍謄本を集めるのはたいへんです。ここで法定相続情報証明制度を利用すれば負担を軽減できます。法定相続情報証明制度について解説します。 相続手続きに必要となる戸籍謄本 不動産や銀行預金などの相続手続きにおいて、亡くなった人...
事業承継対策の真実:後継者選定と自社株式の相続対策
事業承継では何を承継するのか 事業承継は、単に事業を次の世代に渡すこと以上の意味を持ちます。このプロセスには、経営者としての地位の譲渡と、経営理念、会社の強み・弱み、社長が築いた信頼の継承が含まれます。経営者としての地位を渡すとは、社長が...
事業承継への漠然とした恐怖:経営者の不安と世代交代の切迫感
事業承継への漠然とした不安 経営者は、ビジネスを続ける意志と同時に、いずれ後継者にバトンタッチしなければならないという現実を理解しています。新聞やセミナーで目にする事業承継の言葉は、経営者に漠然とした不安をもたらします。銀行や税理士からの...
事業承継の課題と解決策:経営者の心理と後継者選びの難しさ
事業承継への抵抗感と経営者の心理 事業承継は、多くの経営者にとって避けたいテーマの一つです。中小企業庁の報告によれば、70代、80代の経営者の中で、事業承継の準備が完了していると回答した企業は半数以下に留まっています。これは、経営者たちが自分...
効果的な相続税対策と不動産活用
金融資産を不動産に変えると評価が下がる 個人財産を現金や金融資産として持っていても、その金額100%に対して相続税がかかります。しかし、不動産として持っていれば、100%ではなく60%程度まで評価額を引下げることができます。 相続税対策の中で最も...
わかりやすい相続税対策:相続税は重いのか?遺産分割のための生命保険活用法
相続税は本当に重いのか? 日本の相続税に関して、「最高税率が50%を超え、相続すると財産が半分になってしまう」という声がよく聞かれます。しかし、実際にはこのような高い税率が適用されるケースはほとんどありません。私が税理士として経験してきた中...
高齢者が知っておくべき相続税対策:課税される相続財産と不動産評価
相続税がかかる財産 お金に替えられるのには、すべて相続税がかかります。預貯金、有価証券、不動産はわかりやすいのですが、預金から引出した現金、美術品にも相続税がかかります。これらの財産のことを「相続財産」と言います。 ただし、例外があります...
遺産相続で相続争いを避ける:家族の法定相続分と遺産分割の基本
遺産分割協議とは 民法では、財産の分け方の目安となる法定相続分が定められています。しかし、必ずしも法定相続分で分ける必要はありません。遺言書があれば、それが優先され、遺言書が無ければ、相続人同士の話し合いで決めます。 「誰がどの財産をもら...