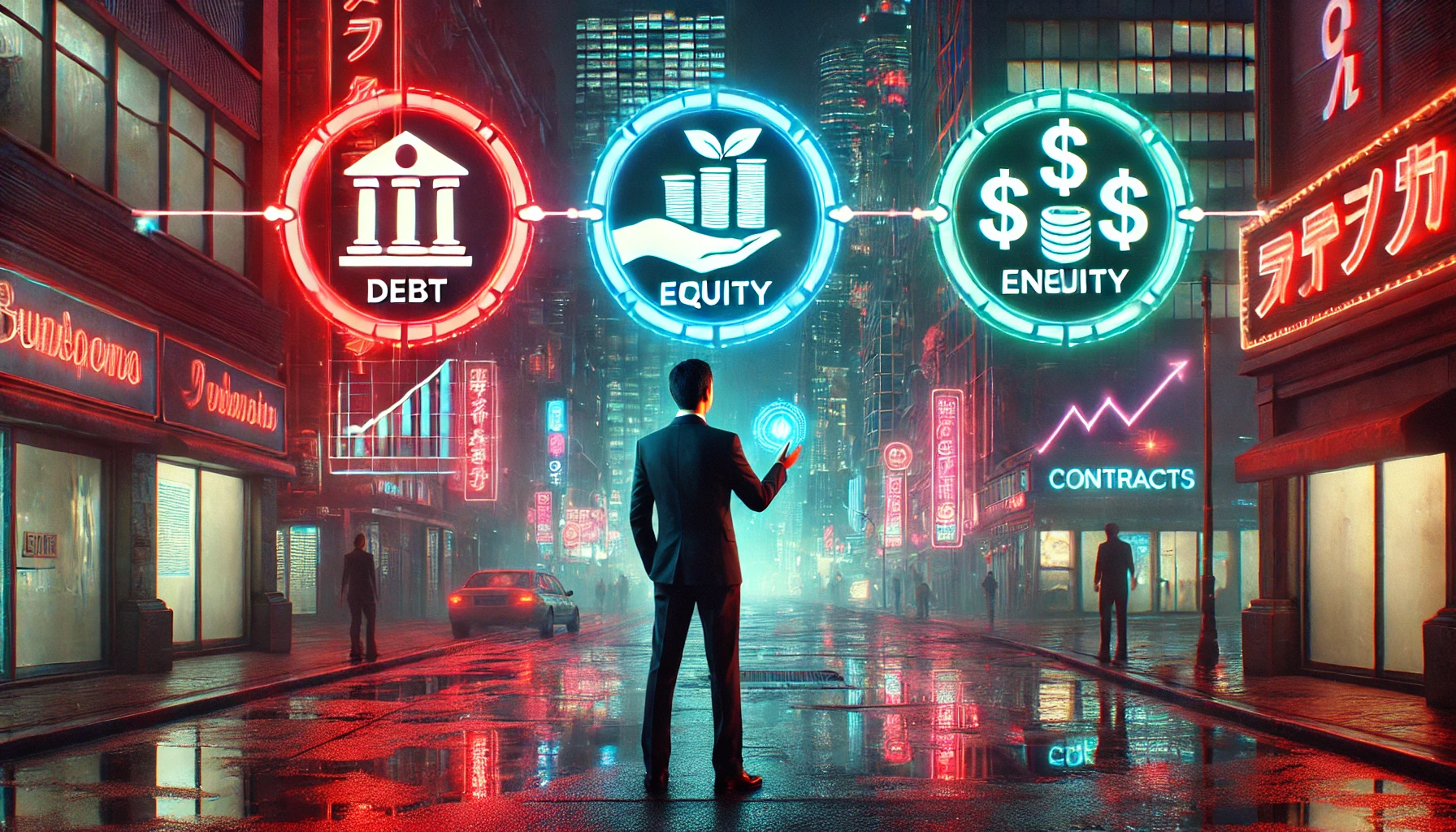03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
資本の払戻し・出資(持分)の払戻しは異なる!払戻しの会計・税務

株主など出資者が払い込んだお金を払い戻すこと(出資の払戻し)と、会社の資本金と剰余金を減少させる手続き(資本の払戻し)は、とても似ていますが、会計・税務において大きく異なります。特に合同会社の相続において持分を払い戻すケースが問題となります。ここでは、これらの異同を解説しましょう。
「資本の払戻し」は会社の純資産の減少
株式会社では、資本金の額そのものを直接に払い戻す(有償減資)ことは、簡単に行うことができるものではありません。会社法の規則が厳格だからです。
この場合、いったん資本金の額の減少手続きを実施し、減少した資本金を資本剰余金に振替えて払戻しの手続きを実施する必要があります。
これを仕訳で表記すれば次のようになります。
(借)資本金 ××× (貸)資本剰余金 ×××
(借)資本剰余金 ××× (貸)現預金 ×××
税法においても、資本の払戻しは、株式に係る剰余金の分配であって、それが資本剰余金の減少を伴うものと定めています。
「出資の払戻し」は出資者の投資回収
一方、とても似たような取引となりますが、出資者(オーナー)が払い込んだ出資金を払い戻すケースがあります。
たとえば、株式会社における自己株式の取得、合同会社における出資持分の払戻し、「持分の定めのある医療法人」における出資持分の払戻しや消却を行う場合です。これらによって、資本金又は出資金を直接に減少させることができます。
合同会社における出資の払戻しがどういう意味なのか確認します。
合同会社の社員は、会社に対して、すでに出資金として払込んだお金の払戻しを請求することができます。
持分会社では、社員は連帯して債務を弁済する責任を負うため、その債権者は会社財産だけでなく、社員の個人財産もあてにすることができます。そのため、会社財産の流出も許容され、合同会社では出資の払戻しが認められているのです。
ただし、合同会社は、全社員が出資額までしか債務の弁済責任を負いません(有限責任社員)。それゆえ、会社財産がむやみに流出してしまうと、債権者の利益を害することになります。そこで、合同会社では出資の払戻しが制限されているのです。
具体的には、合同会社の社員は、出資の払戻しを請求するために、定款を変更して「出資の価額」を減額させなければいけません。
また、定款変更を行ったとしても、一定限度額を超える出資の払戻しはできないことになっています。
出資の払戻しのためには、資本金を減少させる必要がありますが、合同会社が資本金を減少する場合には、その債権者は、会社に対して、資本金の減少について異議を述べることができることとされています(債権者保護手続き)。
会社法における出資の払戻しの制限規定
合同会社では、出資の払戻しが可能であるものの、債権者を保護するために、制限が課せられています。会社法の規定を確認しましょう。
| 第632条【出資の払戻しの制限】 ① 第624条第1項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。 ② 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(出資払戻額)が、請求日における剰余金額(資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。)又は出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第624条第1項前段の規定による請求を拒むことができる。 |
つまり、資本金の減少額、または、資本金の減少額と剰余金の合計額のうちいずれか小さい金額までしか払い戻しできないということです。
小さい金額までとなると、たくさん剰余金があっても、出資者はその剰余金の払戻しができないのか?と疑問が生じるかもしれません。これは剰余金の分配を行えばよいというだけなので、問題ありません。
この規定ですが、合同会社の社員は、定款を変更してその出資を減少する場合を除いて、会社に対し、出資の払戻しを請求することができないというものです。これは債権者保護が目的でしょう。
また、出資の払戻し額が、その請求日における剰余金又は出資額を減少した金額のいずれか少ないほうを超える場合、その出資の払戻しをすることができないとされます。これと同時に会社側では、出資の払戻し請求を拒否できるとされています。社員であった期間に増やした(減らした)財産については、その社員の持分に反映させるということでしょう。
出資の払戻しと資本の払戻しにおける税務上の異同
資本の払戻しも出資の払戻しも、払戻金額が資本金を超える場合には、その超える部分が「みなし配当」として取り扱われます。配当金という取り扱いです。
また、払戻金額のうち「みなし配当」以外の部分は、株式等の譲渡収入とみなされています。それゆえ、出資者(オーナー)の立場から見れば、当初出資したときの金額と払戻金額が異なるときは、株式等の譲渡損益が生じることになります。
ここからが重要です!
出資の払戻しを行った場合、払戻金額が資本金以下であれば、みなし配当は発生しません。自分が払い込んだ金額の全額を回収できていないわけですから、当然ですね。
これに対して、資本の払戻しに関しては、その払戻しが資本金からなされていても、法人の純資産に利益剰余金がある限り、「みなし配当」が発生しますので注意が必要です。これは会社の純資産の減少を行っているからです。
なお、出資の払戻しが資本金以下であっても、それが特定の出資者に対するものである場合には、他の出資者に対して「みなし贈与」課税が生じるケースがあるため注意しましょう。
退社に伴って持分を払戻す場合
次に、退社した社員の投資回収に関する規定を見てみましょう。
上述した出資の払戻し制度は、社員が退社すること、そのとき当初の出資額を全額回収することは想定していませんでした。しかし、社員が辞めることもあるため、その際の対応方法も想定しなければいません。
この点、合同会社を退社した社員は、持分の払戻しを受けることができるようになっています。
「持分の払戻し」という新たなキーワードが出てきました。これは何でしょうか?
持分の払戻しは、払込みしたお金の金額を限度とする出資の払戻しとは異なり、退社時における持分会社の純資産の大きさに応じて行われます。
具体的には、退社時の純資産のうち、退社した社員の出資割合に対応する金額を払い戻すということです。時価ではありません、簿価ベースの純資産です。
ただし、合同会社の場合、出資の払戻しと同様、退社に伴う持分の払戻しについて制限があります。
具体的には、持分の払戻金額が、その払戻す日における資本金および剰余金の合計額を超えている場合には、債権者は、持分の払戻しについて異議を述べることができるものとされています。債権者を保護するための規定です。
また、合同会社が債権者保護手続きを経ないで、勝手に持分の払戻しを行った場合、その業務を執行した他の社員は、持分の払戻しを受けた社員と連帯して、持分払戻し金額に相当するお金を会社に支払わなければならないこととされています。社員の責任です。
その他資本剰余金の取り崩しに係る法務
出資の払戻しを行うと、資本金または資本準備金を減少して、その他資本剰余金に振り替えなければいけません。その他資本剰余金は、剰余金の配当の財源になります。
(借)資本金 ××× (貸)資本剰余金 ×××
(借)資本剰余金 ××× (貸)現預金 ×××
会社法上の剰余金の分配規制のもとでは、その他の資本剰余金は、利益剰余金と同様に分配可能額を構成することとなります。
そこで、出資を払戻すために、その他資本剰余金を取崩した場合の法務・会計・税務を確認しておきましょう。
会社法上、資本金の減少と、株主に対する払戻しは区別されています。
資本金の減少は、資本金を減少させて、同額のその他資本剰余金を増加させる取引です。
出資者に対して資本の払戻しを行う場合は、そこで発生したその他資本剰余金を原資として剰余金の分配を行うことになります。
【資本金の減少によって発生したその他資本剰余金を原資として剰余金の配当を行う場合】

株式会社を前提としますと、資本金の減少に係る決議は、原則として株主総会の特別決議事項であり、剰余金の配当に係る決議は、原則として株主総会の普通決議事項です。
これら二つの決議は同じ株主総会において、たとえば「第1号議案 資本金の減少の件」および「第2号議案 剰余金の配当の件」と付議して行うことが可能です。すなわち、効力発生日を同じ日と定めて決議することにより、資本金の減少と同じ日に剰余金の配当を行うことが可能です。
もちろん、資本金の減少によって発生したその他資本剰余金をそのまま計上しておくことも可能です。
また、利益剰余金の額がマイナスであるときのそのマイナスに充当することもできます。
会社法では、剰余金の中の勘定科目の変更を想定しているだけで、別途積立金の積立て・取崩のような利益剰余金の中での振替だけでなく、その他資本剰余金からその他利益剰余金のマイナスへの充当(欠損てん補)も可能です。
(借)資本金 ××× (貸)その他資本剰余金 ×××
(借)その他資本剰余金 ××× (貸)利益剰余金 ×××
その他資本剰余金の取り崩しに係る会計処理
会計処理については、その他資本剰余金や利益剰余金の分配を行う法人側の会計処理と、その配当を受ける法人または個人側の会計処理の両面から考える必要があります。
先にその他資本剰余金や利益剰余金の分配を行う法人側の会計処理を見ていきましょう。
会計上も、会社法の取扱いに合わせて、資本金の減少と剰余金の配当を区別して取り扱います。資本金の減少については、資本金を減少し、その他資本剰余金が計上される認識をします。
(借)資本金 ××× (貸)その他資本剰余金 ×××
その他資本剰余金を原資として剰余金の配当を行う場合は、会計上、その他資本剰余金の減少を認識します。税務上はみなし配当が生じる場合があり、みなし配当に係る源泉所得税等の徴収が必要になります。
(借)その他資本剰余金 ××× (貸)現金預金 ×××
(貸)預り金(源泉所得税) ×××
次に、その他資本剰余金を原資とした剰余金の配当を受ける法人の会計処理を見てみましょう。
株主である法人が、その他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、それが売買目的有価証券である場合を除き、受取配当金の金額を投資有価証券(資産)の帳簿価額から減額します。
(借)現金預金 ××× (貸)投資有価証券 ×××
なお、配当金を計上する際の会計処理ですが、相手方がその他利益剰余金の処分を行っているのか、その他資本剰余金の処分を行っているのか、受け取った立場ではわからないはずです。その場合は、受取る法人側は、受取配当金として計上することができます。
その後、その他資本剰余金の処分によるものであることが判明した場合には、その時点で会計処理を修正すればよいでしょう。
その他資本剰余金を財源とする配当に係る法人税法上の取扱い
その他資本剰余金を原資とする剰余金の配当を行った場合、税務上、自己株式の取得と同様に、資本の払戻しとして取り扱われます。よって、「みなし配当」が発生する可能性があります。
この場合、みなし配当を定めた法人税法24条1項の規定に従います。すなわち、自己株式の取得の場合と同様に、(1)資本金等の減少額と、(2)交付金銭の額(払戻金額)を比較し、(2)払戻金額が(1)資本金等の減少額を上回る場合は、その超過額について利益積立金額の減少として処理します。
その他資本剰余金を財源とする配当を受けた法人株主の会計処理
一方、その他資本剰余金を原資とした配当を受ける側が法人の場合、その税務上の処理は以下の通りとなります。
すなわち、その他資本剰余金を財源とした配当を受ける法人においては、資本金等の減少部分に対応する金額が株式の譲渡収入とされ、利益積立金額の減少部分に対応する金額が受取配当金とされます。
出資している会社が子会社であった場合、その他資本剰余金の処分による配当を受けた場合は、子会社株式の帳簿価額から減額することになると考えられます。
(借)現金預金 ××× (貸)子会社株式 ×××
ただし、完全支配関係がある法人間で配当が行われた場合には、株式の譲渡収入と同額を譲渡原価とするものとされており、計算上、譲渡損益を計上できないようになっています。
結果として、譲渡損益に相当する額は、資本金等の額を加減算して処理する(損益ゼロ)ことになります。
これは、非適格組織再編によって巨額の譲渡損を意図的に創出するような租税回避行為を防ぐための規定だと思われます。
一方、完全支配関係がある法人間で配当が行われた場合、その配当を受ける法人が有する株式は完全子法人株式等に該当するので、受取配当金は全額益金不算入となります。
株式会社が合同会社に出資することは可能か?
合同会社の機関を大まかなイメージで申し上げますと、「出資者」=「経営者」という概念になります。合同会社は、出資者を「社員」と言います。社員は自ら会社経営を行うのです。
そして、社員の中で、経営に参加する者を「業務執行社員」、出資だけして経営に参加しない者は、そのまま「社員」となります。
よくある質問ですが、合同会社に対して、法人(株式会社など)も出資することが可能です。株式会社が出資者になり、出資持分を取得することも可能なのです。
ただし、出資者が法人となると、法人が社員に就任することになり、現場で会社を代表して働くことは理論的に不可能です。出資した株式会社が、合同会社の職務執行者を決めるということになるでしょう。
出資者(社員)が、複数いる場合、代表社員(業務執行社員)となった株式会社は、業務執行者の選任を決定後、速やかに他の社員に通知をしなければいけません。
なお、この業務執行者の住所、氏名は、登記事項となり、合同会社の登記簿に業務執行者として登記されることになります。