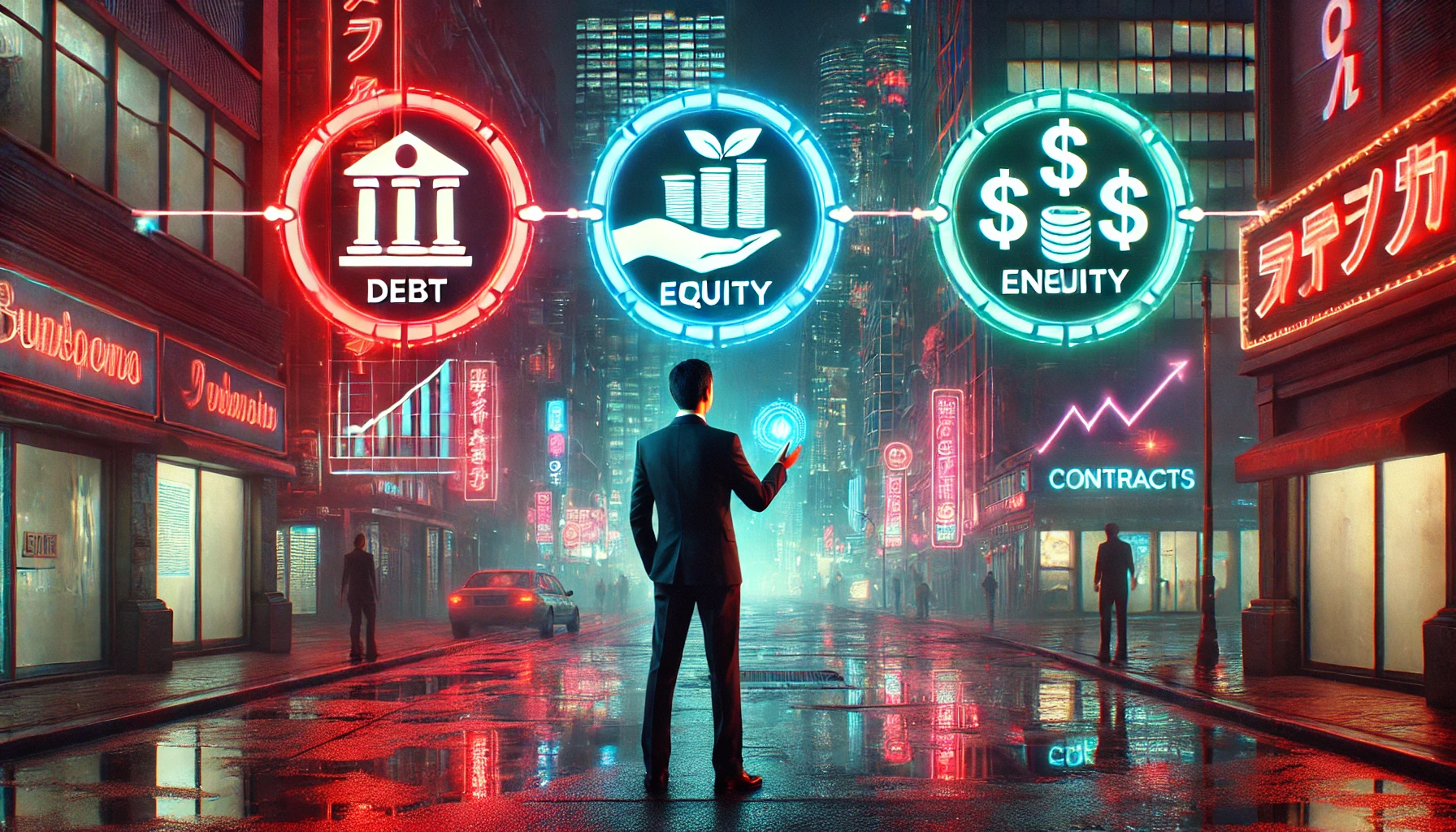03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
事業承継税制も使える!子供への事業承継は株式の贈与が基本

現経営者が株式を相続時まで持ち続け、相続時に事業承継が行われるケースが見られますが、それでは遅すぎです。事業承継は相続時ではなく生前に行われるべきでしょう。今回は、生前に株式を贈与する方法を解説いたします。また、税金ゼロで事業承継が可能となる法人版事業承継税制について解説いたします。
優良企業の事業承継では税金が問題に
親族内承継とは、現経営者から子供や娘婿など親族に対して事業承継を行うことをいいます。通常は、親から子供に株式を承継し、合わせて社長交代することによって、親族内承継が行われます。
株式を承継するタイミングは、大別すれば、相続時と生前に分けられます。相続時に株式を承継するということは、現経営者が死ぬまで株式を持ち続けるということです。これでは経営権の移転の時期が遅すぎます。後継者候補も「いつ自分が社長になるのだろうか?」と心配しているはずです。それゆえ、後継者が社長になる適切なタイミングを捉えるため、通常の事業承継では、生前に株式を承継することを考えます。
生前の株式承継は、大別すれば、無償譲渡(贈与)と有償譲渡の2つの方法となります。さらに、贈与については、暦年課税制度による贈与、相続税精算課税制度による贈与、納税猶予制度による贈与の3つの方法があります。どの方法によった場合でも、株式承継の際に何らかの税金が課されてしまうことは避けられません。
株式承継に課される税金(所得税・贈与税や相続税)の大きさは、自社株式の評価額の大きさに比例して大きくなります。つまり、優良企業であればあるほど、自社株式の評価額は高くなり、税負担が重くなるのです。
業績好調の会社を経営するオーナー経営者が自社株式を保有していると、毎年の利益を計上するたびに、その自社株式の評価額は、どんどん上昇していきます。純資産の大きさや利益額の大きさが評価額の計算要素となっているからです。優良企業であれば、株式承継に伴う税負担は、重要な問題となります。
暦年贈与で株式をコツコツ贈与が基本
生前贈与の3つ方法を理解し、使い分けることを検討しましょう。
まず、暦年課税制度による贈与(暦年贈与)とは、1年間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら非課税、110万円を超える贈与を受けた場合に課税される贈与のことです。
暦年贈与は、何人でも、何度でも使うことできます。贈与を受ける人を増やして、毎年少しずつ贈与を続けていけば、将来の相続税の節税となります。
この節税効果を考慮すれば、相続税よりも贈与税の税率が低いかぎり、早めに贈与しておいたほうが得策だということになります。現経営者が、時間をかけて少しずつ後継者に株式を贈与していくことが、相続税対策となるのです。中小企業の事業承継では、この方法が基本となります。
生前贈与を行う際の手続き上の注意点は、口約束だけで贈与を行い、証拠が何も残っていない場合、生前贈与が否定されてしまうおそれがあることです。法人税申告書の別表二「同族会社の判定に関する明細書」における「株主等の株式数等の明細」を書き換えておきましょう。また、正式な贈与契約書を作成しておくことも必要です。それらは顧問税理士に依頼しましょう。
相続時精算課税で一気にまとめて贈与できる
優良企業で自社株式の評価額が比較的高くなっており、毎年110万円の基礎控除を活用するだけでは、節税効果が小さすぎる、あるいは株式承継のスピードが遅すぎて、現経営者の将来の相続までに間に合わないというケースもあります。
そのような場合、相続時精算課税制度による贈与を利用して、株式評価額の低いうちに一気に株式承継を完了してしまう方法があります。
この相続時精算課税制度は、節税方法ではなく、課税の先送りです。税金の一部を贈与時に前払いしておきますが、相続発生時には全額を精算しなくてはなりません。具体的には、贈与財産を相続財産に加算して、相続税を支払うのです(すでに支払った贈与税を控除します)。
しかし、相続税の課税価格は、相続時ではなく贈与時の株式評価額で計算されるため、評価額の上昇が続いて、贈与時よりも相続時の税負担の増大が想定されているようなケースでは、生前に贈与しておくことが節税効果をもたらします。
相続時精算課税制度による贈与の適用を決めた場合、贈与を行うタイミングにおいて、自社株式の評価額を引下げます。たとえば、贈与する直前期を現経営者が引退する年度とし、多額の退職金を支払うのです。決算を赤字とすれば、自社株式の評価額が下がるでしょう。そのタイミングで株式をまとめて贈与すればよいでしょう。
以上のように、暦年課税制度、相続時精算課税制度による贈与が、親族内承継における株式承継の基本となります。
加えて、近年は、贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)による贈与が増えてきています。ただし、この方法は、制度適用申請の手続きを行うためコスト負担(事務作業や専門家報酬)が比較的重いため、税負担が小さい小規模企業が適用すると、メリット(節税効果)よりもデメリット(コスト負担)のほうが大きくなってしまいます。
それゆえ、大まかにイメージとして、この方法は、自社株式100%評価額が1億円を超えるような中堅企業が使うものだと思ってください。株式評価額が1億円を超えないのであれば、他の2つの贈与の方法を使えばよいでしょう。
公平な遺産分割は支配権争いを招く
いずれの生前贈与の方法によっても、むやみに贈与する相手を増やしてしまうべきではありません。後継者となる子供だけでなく、後継者以外の子供や孫に株式を所有させてしまうケースがありますが、支配権が分散し、後継者の地位が不安定になってしまいます。
まだ兄弟間での争いであれば喧嘩を回避することも可能かもしれませんが、孫の世代になり、従兄弟の関係で支配権を争うような事態になると、人間関係の悪化を修復することが、極めて困難になります。
遺産分割を公平にすべきか、後継者に集中させるべきか、とても悩ましい問題です。後継者に株式を集中させるとすれば、後継者ではない子供たちにはそれ以外の財産を渡して、財産をバランスよく分けることができるように準備しておく必要があります。生命保険や不動産といった資産を持っておくのです。顧問税理士にぜひ相談してみましょう。
法人版事業承継税制で税金ゼロに!
法人版事業承継税制とは、中小企業経営承継円滑化法に基づく制度で、非上場株式についての贈与税の納税猶予制度のことをいいます。会社の代表権を有していた先代経営者が、後継者に対して自社株式の贈与を行った場合、先代経営者の相続発生時まで、全ての株式について課税価格100%(特例措置)に対する納税が猶予されるというものです。
その後、先代経営者に相続が発生したとき、猶予された贈与税が免除され、代わりに相続税が課されることとなります。この際、制度の要件を満たすことによって、贈与税の納税猶予制度から相続税の納税猶予制度へと移行します。すなわち、先代経営者が死亡しても相続税は課されず、後継者の次の事業承継が行われるまで、その納税が猶予されることになるのです。
この制度はやや複雑ではありますが、一言で言えば、後継者の贈与税や相続税がゼロになるということです。贈与税の納税猶予制度と相続税の納税猶予制度は一体となっており、これらの制度の適用をリレーのように続けることによって、自社株式に係る贈与税および相続税の負担が、将来にわたって大幅に軽減され続けることになります。
ただし、事業承継税制を適用するには、5年間平均で雇用8割を維持しなければいけない、5年間は後継者が代表から退任してはいけない、次の事業承継までに後継者は自社株式を譲渡してはいけないなど、厳しい適用要件が課されることになります。これらの要件を満たすことができない場合には制度適用が取り消しされ、納税猶予されている税金を、利子税と合わせて納付することになります。
複数の株主から複数の後継者への事業承継も対象に
先代経営者が発行済株式100%を所有していれば、株主1人による贈与となって単純な話ですが、自社株式を親族に分散させているケースも多く、その場合、先代経営者以外の株主が持っている自社株式の承継に伴う税金が問題となります
これについては、近年の制度改正によって、先代経営者以外の株主から後継者に対して贈与された株式も事業承継税制の対象になりました。ただし、先代経営者からの贈与が先行して行われ、その贈与から5年以内に先代経営者以外の株主からの贈与が行われなければいけません。その順序と期限に要件が設けられています。
また、後継者は1人ではなく最大3名となりました。後継者1人当たり10%以上の株式の贈与を受けるのであれば、3名まで後継者(代表者)として、事業承継税制が適用されることとなりました。
事業承継税制の適用要件を確認しておこう
贈与税の納税猶予制度を適用するためには、対象会社の要件、先代経営者の要件および後継者の要件の3つを満たさなければいけません。
| 【対象会社の要件】
1. 経営承継円滑化法に規定される中小企業であること(資本金または従業員数に上限があります) 2. 上場会社、風俗営業会社に該当しないこと 3. 資産保有型会社・資産運用型会社ではないこと |
資産保有型会社とは、自ら使用していない不動産(賃貸用・販売用)・金融資産・現金預金等(特定資産)が総資産の70%以上を占めている会社をいい、資産運用型会社とは、これらの特定資産の運用収入が総収益の75%以上となる会社をいいます。
ただし、これには例外があり、一定の事業実態がある場合には、資産保有型会社等に該当しないものとみなされ、事業承継税制が適用できるものとされています。すなわち、3年以上、従業員5人(社会保険に加入する親族外の者に限ります)を雇用して、事業を営むことです。
| 【先代経営者(贈与者)の要件】
1. 過去に会社の代表者であったこと 2. 贈与時までに、代表者を退任すること(有給役員で残ることは可能。) 3. 贈与の直前において、先代経営者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと 4. 株式を一括して贈与すること |
| 【後継者(受贈者)】
1. 会社の代表者であること 2. 20歳以上で、かつ役員就任から3年以上経過していること(事業承継税制を適用したいのであれば、3年前までに取締役に就任しておかなければいけません) 3. 贈与後、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること |
以上のような要件です。
一見して厳しいように見えるかもしれませんが、実務の現場において、これらの要件が障害となって、事業承継税制の適用をあきらめるケースは、それほど多くありません。経済産業省は可能なかぎり多くの中小企業に適用してほしいと考えており、税制改正のたびに適用要件は緩和されてきたからです。
税金ゼロでも遺産分割の問題は解決しない
確かに贈与税の納税猶予制度を適用すれば、税負担ゼロで株式承継を行うことができます。ただし、この制度は、自社株式の評価額が高くなってしまった会社の経営者が使うべきものです。しかも、自社株式は、基本的に後継者へ集中することが予定されています。
この場合、先代経営者の個人財産の大部分が自社株式となっているとすれば、それを後継者である子供に集中してしまうと、遺産分割のバランスが悪くなってしまうのです。つまり、後継者ではない子供に残される財産が相対的に小さくなり、彼らの遺留分を侵害しておそれがあります。兄弟仲良しであれば気にすることはないかもしれませんが、親が他界した後に兄弟の仲が悪くなるケースもあるため、遺産分割は要注意です。
そこで、中小企業経営承継円滑化法には、納税猶予制度に加えて、民法特例が定められています。この特例は、経営者から後継者に贈与とされた自社株式について、遺留分の算定基礎財産から除外すること(除外合意)、または、計算に使う価額を固定すること(固定合意)ができる制度です。
納税猶予制度に加えて民法特例まで適用するとすれば、手続きがとても煩雑で、面倒だと思われるかもしれません。しかし、都道府県庁や税務署に提出する申請書類の作成は、税理士がサポートしてくれます。一人で悩まずに、顧問税理士に相談してください。事業承継を成功させるため、これらの制度の活用を検討してみましょう。