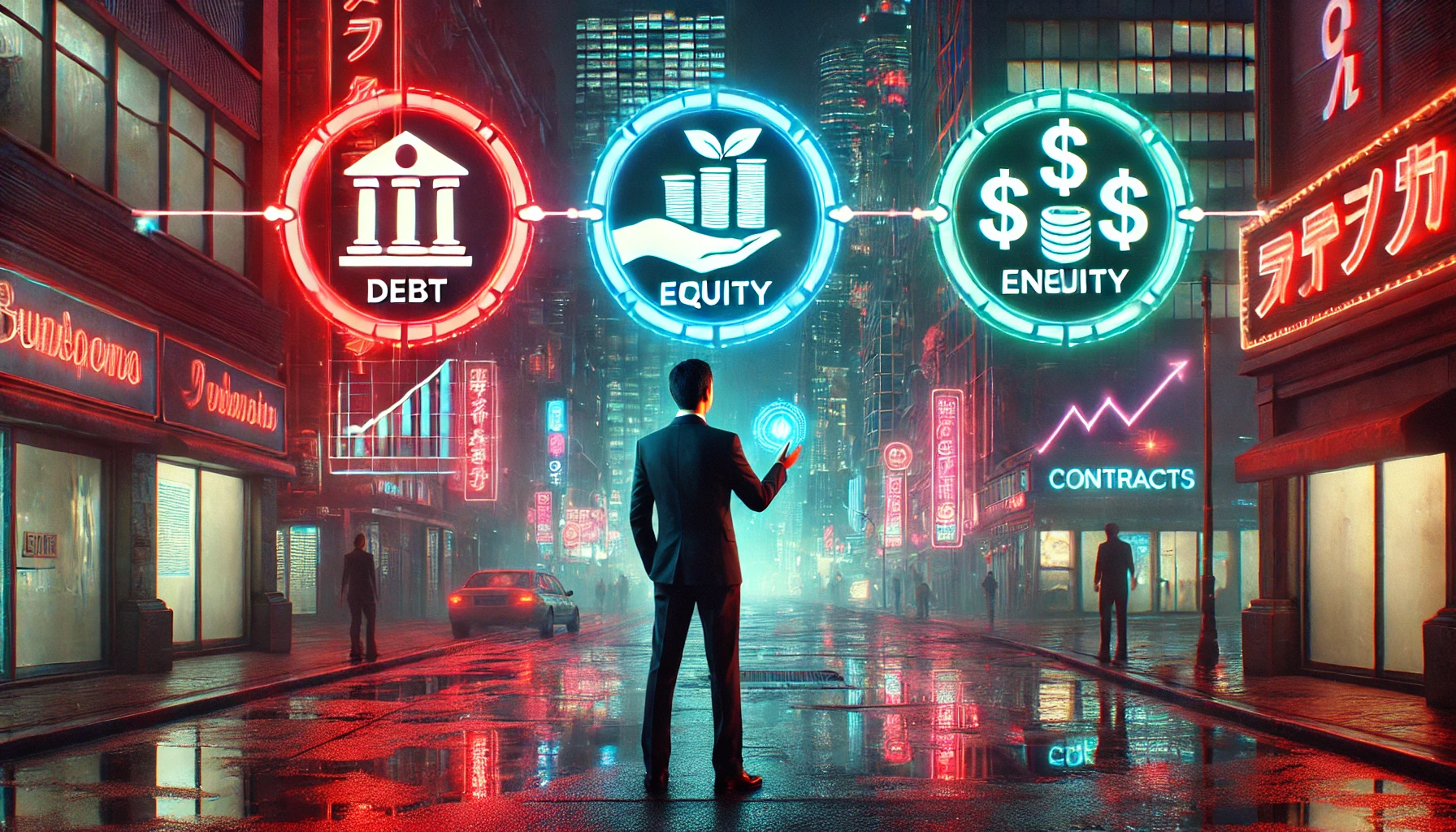0120-1000-77/03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
経営統合を目的とするM&Aはどのように進めるのか?

社長交代のため円滑に経営権を引き継ぐには
親族外事業承継(M&A)の取引が実行された後は、売り手側の経営者は会社の支配権を失い、経営者の立場から解放されることになります。
しかし、通常はそれで終わりではなく、事業価値源泉を円滑に引き継ぐため、取引実行後も一定期間は対象会社の経営に関与する取り決めが行われるケースが多いようです。その関与の方法は、会社の個々の事情に応じたものとなります。
買い手は新しいオーナーとなり、買収した事業の経営に着手することになります。それゆえ、売り手は事業価値源泉を新しいオーナーに円滑に引き渡し、徐々に経営から抜けることになります。
ここでは、売り手側の経営者が段階的に引退することが重要です。すなわち、適当な引継期間を設け、「社長交代したらそれ以降は一切会社に顔を出さない」といった急な動きをするのではなく、残された従業員や取引先によって継続的に事業価値が生み出されるよう、一歩引いた立場で、当面の間は出社して、事業の継続をサポートしなければいけません。
ただし、前経営者の役職をどうするのか、常勤にするのか非常勤にするのか、無報酬にするのか報酬ありにするのか、実際に何をやってもらうのか、いつまで関与するのか、といった条件については、会社の個々の事情に合わせて決めることになります。
前経営者が「顧問」として残る方法
前経営者の処遇の種類として、第一に、売り手側の経営者が「顧間」として残るという方法があります。これは、取引実行後に、速やかに社長の座を降りて「顧問」に就任し、後任の経営者は買い手が決めて、新旧経営者の引継ぎに必要な期間として1年から2年程度を設定する方法です。
顧間として残る前、前経営者は代表権を持ちません。当初はほぼ常勤に近いとしても徐々に非常勤としていきます。非常勤顧問となることで月額報酬は低くなりますが、取引実行前に役員退職金を支払うことが可能となります。
しかし、この方法では親族外事業承継(M&A)が行われて前経営者が退いたという事実が対外的に明らかとなります。それゆえ、売却(M&A)の事実が取引先との関係に悪影響を及ぼし、事業価値が毀損することのないよう注意する必要があります。
前経営者が「会長」として残る方法
第二に、売り手側の経営者が会長に昇格する方法があります。前経営者が、売却後に会長に昇格し、後任経営者とのツートップ体制で引継ぎを行っていく方法です。
前経営者が、取引実行後すぐに一線から離れることで事業価値源泉が失われてしまうような場合には、これが効果的は方法となります。
会長になる元社長には代表権を持たせないケースのほうが多く、経営の引継ぎが進むにつれ、会長は非常勤とします。
この方法では、前経営者が退任後も引続き重要な役員として残ることになるので、この時点で役員退職金を受け取ることができるかが問題となります。それゆえ、代表権を返上して会長に就任する際、その勤務実態の変化と役員報酬の減額の度合いを調べ、税務上も問題ないか確かめておく必要があります。
前経営者が当面は「社長」として残る方法
第三に、売り手側の経営者が当面はそのまま社長として残り、後任社長は代表権を持つ役員として入る方法があります。前経営者が親族外事業承継(M&A)の後も社長の座には留まるものの、後任の社長候補が代表取締役副社長や代表取締役専務といった代表権を持った役付き取締役として招聘されることになります。
前経営者の事業意欲がまだ旺盛ながら事業承継問題を考慮して早めに第三者承継を決断したような場合や、社長に帰属する取引先等との人間関係が重要な事業価値となっている場合など、経営者個人が持っている事業価値の承継が求められる場合、このような方法も選択肢の一つとなります。
M&A実行で引き継いだ事業の経営体制
買い手が想定する経営方針によって、取引実行後の経営体制が異なります。
子会社として経営を行う方法
一つは、対象会社の経営の自律性を維持させたいと考える場合、子会社として経営を行う方法があります。その場合、法人格の独立性を維持したうえで、買い手の経営への関与を限定的とすることが考えられます。
これは、対象会社を子会社として存続させ、許容できる限り経営の自主性を維持するという方針です。役員構成は買い手から若千名の役員を派遣するものの、代表者の変更も求めません。
こうした経営体制は、経営統合が従業員の反発をもたらすおそれがある場合や、人事制度を明確に区別したい場合、買い手とのシナジー効果が期待できない場合に採用されるものです。
これに対して、子会社としての独立性は維持するものの、買い手として経営に積極的に関与していくケースもあるでしょう。対象会社の代表者が買い手から派遣され、全体の役員構成も買い手から派遣される役員が過半を占めるなど、買い手が経営の支配権を握ることも当然にあります。
こうした経営体制は、対象会社が買い手と同じ事業内容である場合や、事業価値の拡大のためにテコ入れが必要である場合に採用されます。
つまり、新しい経営陣のもとで、ビジネスモデルの変更や新しい経営資源の投入が推進される。
ただし、買い手の支配色が強まると「乗っ取り」というイメージが強まり、優秀な人材の離職などによって事業価値を失うおそれがあります。経営権の移行には、慎重な対応が必要となります。
吸収合併される場合の方法
もう一つは、買い手の会社へ吸収合併する方法です。これによって、人事制度をはじめとする各種制度は、買い手の同じものが適用されることになります。
合併は経営統合のスピードが速いため、シナジー効果を早期に実現させることができます。
しかし、統合作業にかかる現場の負担が大きく、従業員の離職など一時的な混乱を引き起こして事業価値を大きく失ってしまうおそれがあります。合併のために、公認会計士を活用した組織統合プロジェクトを実施するなど、全社的な取り組みが求められます。
M&Aの対象事業と買い手との経営統合
親族外事業承継(M&A)のために株式譲渡や合併が実行されますと、形式的には事業承継は終わりとなりますが、買い手にとっては統合作業が、ここからがスタートすることになります。
親族外事業承継(M&A)のメリットは、買い手とのシナジー効果を発揮させ、事業価値を高めることです。両社ともに不足する経営資源を補完する、あるいは、自社の強みをさらに強化するといった目的も、シナジー効果の発揮によって初めて実現することができます。
親族外事業承継(M&A)の現場では、取引は実行したものの、期待したほど事業価値が生み出されないという悩みを聞くことがあります。調査結果の統計データを見ても、「統合後の利益拡大効果が期待したほど得られなかった」という回答が多いようです。これは、取引実行の後の統合作業(PMI)に失敗するケースが多いからでしょう。
買い手との経営統合について、取引実行までに検討できるような余裕あるケースは少ないため、取引実行後にようやく統合作業を開始することがほとんどです。
しかし、経営統合を確実に成功させようとするのであれば、取引実行前から統合の準備作業を行っておくべきでしょう。
特に、その統合作業プロセスと経営管理体制は、少なくとも譲渡契約を締結する前から検討を進めておく必要があります。
この際、「企業文化や組織風土」といった最上位の概念から、「人事・組織」や「業務プロセス」、「情報システム」まで、幅広く捉えることが求められます。
M&Aで企業文化や組織風土を統合することはできるか
経営統合の作業として、具体的には、買い手の経営陣、経営企画部門の責任者など、通常は2~3名のメンバーでプロジェクトを構成し、経営統合の目的を明確にします。
その上で、企業文化や組織風土を融合させる具体的な方法を検討します。これらを検討する場合、ビジネスに対する価値観、人材に対する考え方、顧客への対応方針などの理由によって両社の文化が衝突し、結果として事業価値が失われてしまうことがあります。
そうした事態を避けるために、早い段階で企業文化や組織風土の違いを認識し、無駄な摩擦を起こさないように、たとえば、組織を統合させる前から段階的な人材交流を行い、意見交換を実施しておきたいところです。
M&Aで人事・組織を統合することはできるか
経営統合における人事・組織統合においても、「組織は戦略に従う。」といわれるように、買い手の経営戦略に適合する組織を作ることが重要です。
人事・組織統合の目的の一つに経営効率化があり、経理部などの間接部門は1つに統合すべきことには疑問の余地はありません。
しかし、両社の重複するポジションが整理されてしまうと従業員のリストラを強いることとなります。
人事・組織統合というのは、従業員のモチベーションという重要な事業価値源泉に影響を与える作業であることから、従業員が納得して受け入れて、引き続き活躍できるような配慮や取組みが必要です。
業務プロセスを統合することはできるか
最後の課題が業務プロセスの統合です。業務統合がうまくいかないと、従業員個人の日常業務に支障をきたし、事業価値を失うおそれがあります。
業務統合の検討は、課長や係長など現場に近い管理職を巻き込んで行わなければなりません。
業務統合の主たる目的は、業務効率化によるコスト削減効果です。両社において重複している業務があり、それらを統合することで規模の経済が生まれるのであれば、コスト削減効果は大きいでしょう。
特に、規模の経済は事業価値を増大させる手段として、最もわかりやすいものであるため、事前に計画しておき、確実に実現させたいものです。
ただし、重複業務を減らすために人員削減を伴うリストラや解雇を実施し続けると、従業員のモチベーションを落とし、事業価値を失うことにもなりかねません。組織統合の作業と同様、会社内部における配置転換などを検討したいところです。
M&Aで情報システムを統合することはできるか
情報システムの統合は、業務統合と密接に関連し、会社を動かす基盤となる領域です。システムが高度なものであればあるほど、その統合にかかる労力とコストは多大なものとなります。
情報システムの統合は、基本的に一本化です。異なる情報システム間で機能の比較を行い、高機能なシステムに一本化することになります。
ただし、情報システムの切替えは日常的な業務プロセスの変更を伴うため、従業員にとっては煩わしい作業が生じます。
従業員へ切替え作業のやり方を丁寧に説明すべきですが、業務プロセスの変更のために時間的な余裕がない場合は、社内に混乱を起こさないよう、その切替えのタイミングに注意すべきでしょう。
日常業務の混乱を避けるためには、一定期間は両方の情報システムを併用し、移行期間を数年設けた後に統合するという方法も考えられるかもしれません。