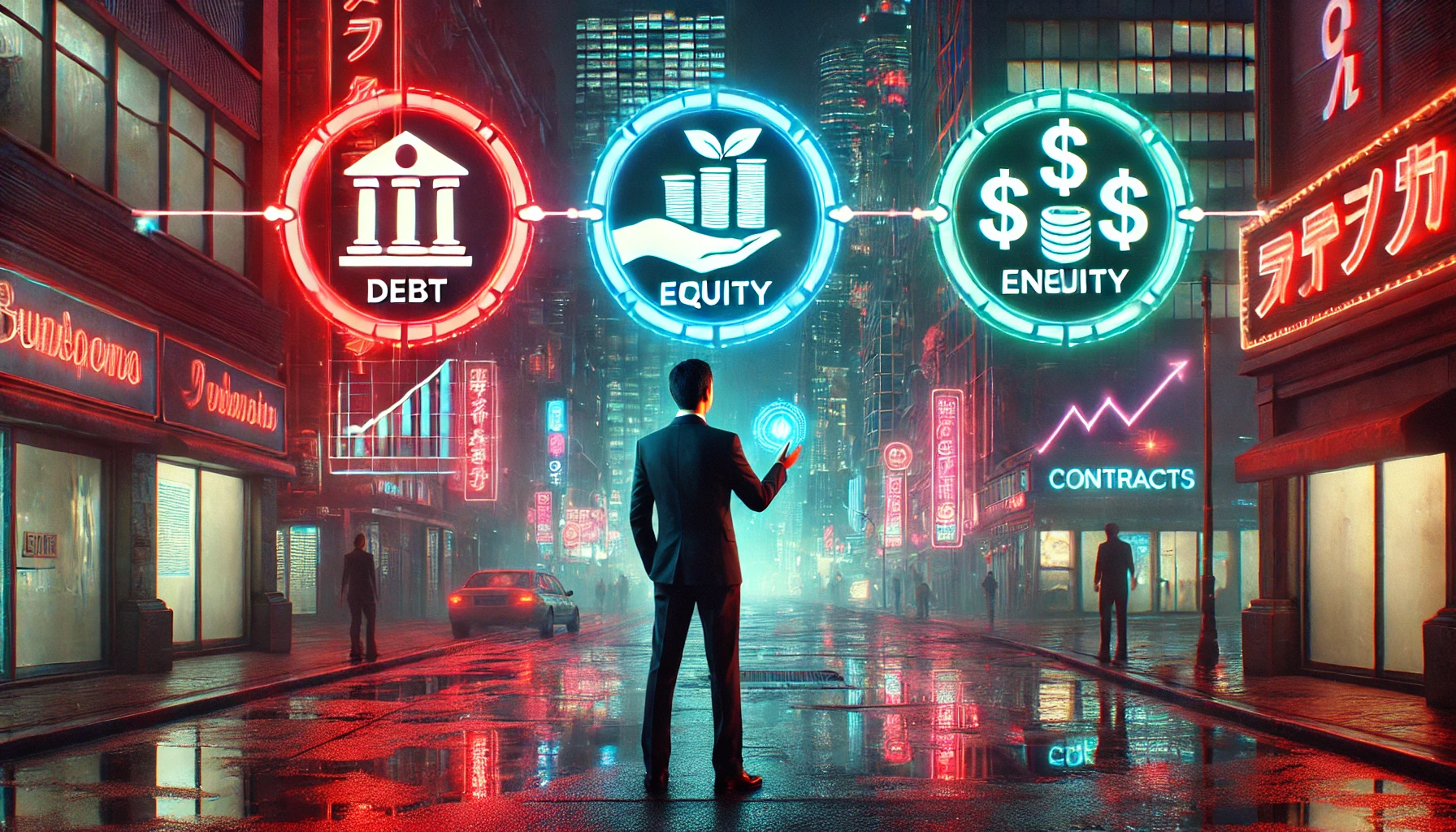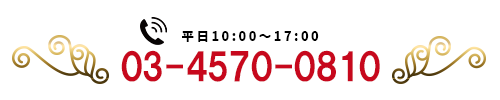03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
起業家必見!負債・出資・現金化・補助金まで、資金調達のすべてを徹底解説

事業立ち上げの壁は「資金」
新たに事業を始める際、多くの起業家が最初に直面する課題が資金調達である。とりわけ中小事業者やスタートアップにとって、自己資金だけで初期費用や運転資金を賄うのは難しい。調達手段には多様な選択肢があり、それぞれ資金の性質やリスク、企業に求められる要件が異なる。
資金調達は主に「借入」「出資」「資産の現金化」「その他の方法」に分類される。本稿では、それぞれの仕組みと特徴を整理しつつ、個人事業主や小規模法人の創業支援事例も交えて解説する。
借入は最も一般的な手法
資金調達手段として最も広く用いられているのが借入である。これは金融機関や投資家から一定期間内に元本と利息を返済する契約のもとで資金を得る方式だ。調達資金は運転資金や設備投資など多岐に活用できる。
主な方法は銀行融資、社債の発行、公的融資、ビジネスローンなどがある。銀行融資には短期と長期があり、短期は日常の資金繰り、長期は固定資産投資などに用いられる。公的機関では日本政策金融公庫が創業者向けに低利融資制度を設けており、開業初期の支援に適している。
借入の利点は、迅速かつ比較的大口の資金を調達でき、経営権を保持できる点にある。借入による資金は自己資本と異なり、企業価値の希薄化を招かない。支払利息は損金算入でき、節税効果も期待できる。
一方で返済義務があるため、キャッシュフローを圧迫するリスクが常に伴う。財務上は負債として計上されるため、自己資本比率の低下要因となる。また、信用力や担保、保証人の有無によって融資可否や条件が左右される。
出資は成長段階に応じた選択肢
出資は、株式などの持分を対価に第三者から資金を受ける方式である。借入と異なり返済義務はないが、経営権の一部を譲渡することになる。
スタートアップ段階では、個人投資家によるエンジェル投資が活用されるケースが多い。出資額は数百万円から数千万円が一般的で、事業の成長性や革新性が評価される。出資にあたっては、優先株式や新株予約権付き契約が用いられることもある。
成長後は、IPO(新規株式公開)によって大規模な資金調達を行う例もある。IPOにより企業は証券市場で株式を公開し、不特定多数の投資家から出資を受ける。近年では東証スタンダードやグロース市場への上場が増加しており、調達額は数十億円規模に達することもある。
出資の利点は、返済不要であり財務負担を増やさずに資金を得られる点である。自己資本比率が向上するため、信用力の強化にもつながる。
他方、株主に議決権が発生するため、経営方針に対する意見や関与を受けるリスクがある。IPOの場合は四半期開示など情報公開義務が発生し、準備には相応の時間とコストが必要となる。
保有資産を活用した現金化
売掛債権や手形、不動産などの保有資産を活用して資金を得るのが資産の現金化である。これは主に短期資金の確保を目的として用いられる。
代表的な手法はファクタリング、手形割引、リースバックなどが挙げられる。ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社に売却し、決済期日前に資金を得る。手形割引は、受け取った手形を金融機関に持ち込み、一定の割引料を差し引いた金額を即時に受け取る方式である。リースバックは、不動産や設備を売却し、同時に賃貸契約を結ぶことで、継続使用しながら資金を確保する方法だ。
資産の現金化は迅速な資金調達が可能であり、財務上の負債計上が不要な点が強みである。ファクタリングの場合は貸倒リスクを移転できるメリットもある。
ただし、手数料や割引料は高くなる傾向があり、長期的には収益性への影響も無視できない。加えて、資産価値が低い場合には十分な資金を確保できないリスクがある。
補助金・クラウドファンディング等の選択肢も
借入や出資とは異なる資金調達手段として、補助金・助成金、クラウドファンディング、ジョイントベンチャーなどの方式も注目されている。
補助金・助成金は、国や地方自治体が事業者の創業や成長を後押しするために提供する返済不要の資金である。たとえば「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などがあり、採択には詳細な事業計画書の提出が必要となる。資金用途に一定の制約があるほか、後払いが原則となるケースが多い。
クラウドファンディングは、インターネットを通じてプロジェクトに共感した支援者から少額ずつ資金を募る仕組みである。リターンとして製品やサービスを提供する購入型、融資型、寄付型などがある。広報効果が高く、商品やサービスの事前マーケティングとしても活用されている。
ジョイントベンチャーは、複数の企業が出資し新会社を設立する形態である。技術・販路・人材などのリソースを共有し、事業シナジーを創出する目的で用いられる。海外進出や新市場開拓時に採用されることが多い。
これらの手法は、目的や事業内容に応じて組み合わせることで、より柔軟で効率的な資金調達が可能となる。
成功事例に見る資金戦略
資金調達の実例として、横浜市で米粉パン店を開業した元会社員のケースがある。同氏は退職金を元手に、日本政策金融公庫から700万円の融資を受け、自治体の補助金200万円も加えて事業を開始した。高齢者の経験や地域の食育支援という社会的意義が評価された。
また、副業としてアパレルECショップを立ち上げた会社員は、クラウドファンディングで96万円を調達し、売掛債権の一部をファクタリングで現金化した。Google Analyticsのデータをもとに成長見通しを示したことで、信用を得たという。
東京都内でフレンチバルを開業した料理人は、日本政策金融公庫から900万円の融資を受けたほか、予約金をファクタリングで資金化した。食品衛生優良店舗認定を活用し、50万円の補助金も得て、初期投資総額1200万円の調達に成功した。
複合的な活用が鍵に
資金調達には単一の手法に依存するのではなく、複数の手段を組み合わせることで、リスクを分散しながら必要資金を確保する戦略が有効である。とりわけ創業初期においては、自己資金、公的融資、資産の現金化、補助金の活用を適切に組み合わせることで、事業の安定と成長を実現しやすくなる。
資金調達は単なる資金確保の手段ではなく、企業の成長戦略や事業計画と密接に関係する経営判断の一部である。起業家はそれぞれの手法の本質を理解し、自社の状況に最も適した資金構成を設計する必要がある。