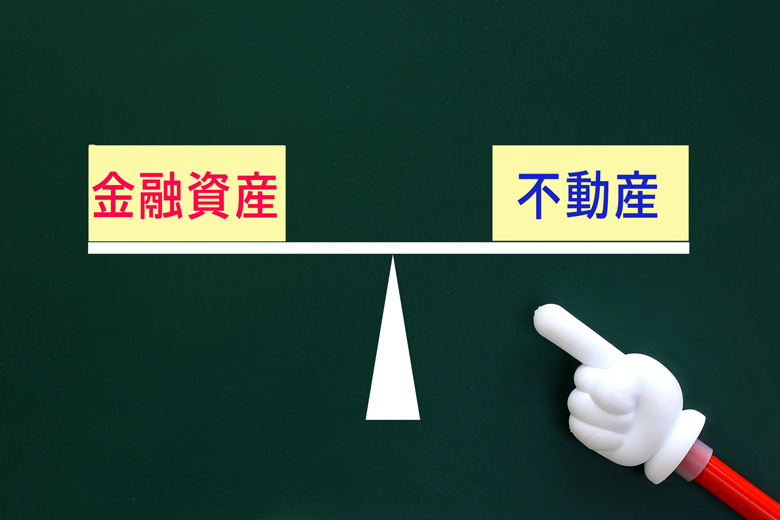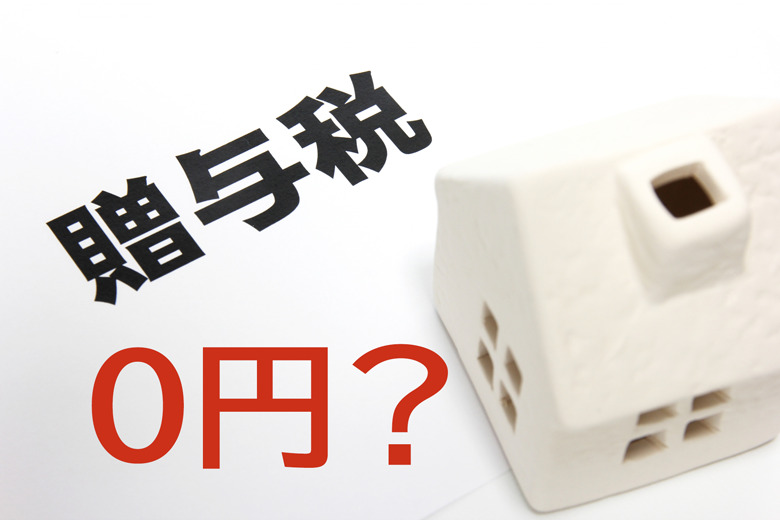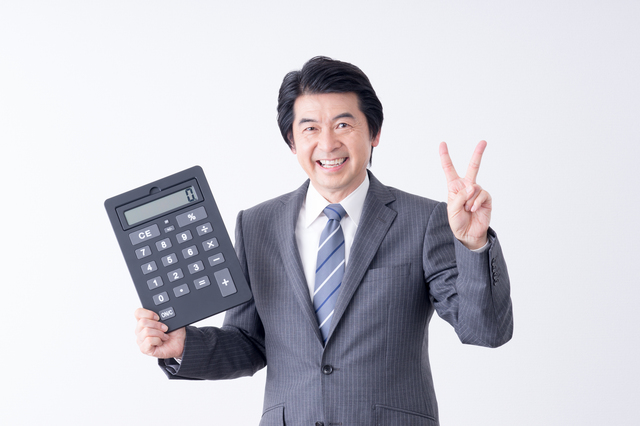0120-1000-77/03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
相続税対策– tag –
-

【自社株対策】中小企業経営者の相続対策と事業承継の基本
自社株式は、会社の「経営権」を表すものであると同時に、企業経営者の「個人財産」です。現預金や不動産のように、子どもたちへ均等に分ければよいというものではありません。今回は、自社株式の相続について考えてみましょう。 自社株式の遺産分割は難し... -

事業承継と節税戦略:持株会社設立と「株特外し」の活用
事業承継は企業の存続と発展に直結する重要な課題です。この記事では、事業承継における株式承継に焦点を当て、持株会社設立や「株特外し」などについて解説します。 持株会社設立のメリット 事業承継には、先代経営者から後継者への株式の承継が伴います... -

ジャニーズ事務所で使われた事業承継税制!ジャニー喜多川氏・メリー喜多川氏の相続税から藤島ジュリー景子氏の納税猶予制度まで!
今回は、ジャニーズ事務所で使われた事業承継税制について解説します。このチャンネルをご覧の方々の中にも、ジャニーズ事務所の相続や事業承継が世間で騒がれているけれど、どうなっているのかと関心している人が多いのではないでしょうか。 そこで今回は... -

【相続税対策】相続時に自社株式の評価額はいくらになるか?類似業種比準価額、純資産価額とは?
非上場であっても会社の株式は相続税がかかります。今回は、相続時に自社株式の評価額がいくらになるか、その計算方法わかりやすくご説明しましょう。 非上場の株式の評価額を計算する目的 非上場であっても会社の株式には相続税がかかります。それゆえ、... -

【相続対策】全体像!相続税、不動産、生命保険まで詳しく解説
相続税負担の重さ 相続税は本当に重いのか? 日本の相続税に関して、「最高税率が50%を超え、相続すると財産が半分になってしまう」という声がよく聞かれます。しかし、実際にはこのような高い税率が適用されるケースはほとんどありません。私が税理士と... -

【タワマン節税】2024年から新しいタワーマンションの相続税評価が変わる!【令和6年度税制改正】
国税庁が「タワマン節税」による相続税対策を封じるため、タワーマンションの相続税評価の計算式を導入します。2024年1月1日以降、相続税評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍以上の場合には相続税評価額が上がり、高層階ほど相続税額が増える見通しです。... -

富裕層の相続税は今後増税になるか?2022年以降の改正に注意!
日本の税収において、相続税は令和3年度(2021年度)でも2.2兆円ほどしかなく、所得税の10分の1程度となっています。まだ増税の余地があることから、現在、政府の税制調査会は、富裕層の税負担を重くする方向に検討を進めています。また、相続直前の暦年... -

銀行や証券会社が提案する「ウェルスマネジメント」とは?
銀行や証券会社の営業マンが「ウェルス・マネジメント」というサービスを売り込んできます。これは生命保険の「ライフ・プランニング」と違うものでしょうか? 【1】 一生涯のライフ・プランニング どんな方でも生命保険の営業マンから商品の提案を受けた... -

相続税対策の基本!まずはここから!
評価の引下げよりも先に資産を減らすこと 相続では、先に相続税の総額が計算されます。すなわち、正味の相続財産(=資産-非課税財産-債務控除)」から基礎控除額を差し引き、その金額(課税遺産総額)を、民法の法定相続分で分けたと仮定してうえで超過... -

相続対策!不動産活用法まとめ
住宅取得等資金贈与の非課税特例 金融資産家にとっての資産承継対策は、相続財産を減らすこと、すなわち生前贈与が基本となります。近年、金融資産家にとって効果的な制度が導入されています。その一つに、住宅取得資金贈与の非課税特例があります。 これ... -

相続の準備をはじめよう!終活はここから!
相続生前対策の必要性 欧米では、資産家の資産の保全およびリスク管理、資産承継のために、総合的な財務戦略が立案されることが一般的です。このような財務戦略のことを「エステート・プランニング」と呼んでいます。 日本には、このような財務戦略の考え... -

相続・事業承継対策!民事信託活用方法を網羅!あなたはどのケース?
高齢の親が認知症になりそうな場合 認知症と財産管理 【お悩み】 父親が高齢で認知症になりそうです。最近は財産の管理ができなくなってきた様子なので、今後のことが心配です。 高齢の父親が、賃貸不動産や多額の金融資産など高額の財産を持っている場合... -

民事信託のすべてがわかる!基礎知識を徹底解説!
はじめに 信じて託すこと 信託とは、「信じて託す」すなわち個人が持っている財産を守りながら、それを人に預けることです。具体的には、本人が自分で財産を管理することに不都合が生じた場合、それを人に財産を預け、預かった人がその財産の管理を行いな... -

不動産所有法人のメリットと節税効果とは?
法人経営による所得税の節税 重い所得税と軽い法人税 2015年度の税制改正において、課税所得4,000万円超の人の最高税率が45%に引き上げられました。それ以外の人も同様に、累進課税が適用される所得税の負担は極めて重いものとなっています。 これに加え... -

資産の組換えで相続税対策!金融商品から不動産へ
財産2億円までの相続税対策 相続税負担は重くない 日本の相続税は、「最高税率が55%と高い。相続のたびに財産が半減して、三世代の相続で財産が消えてしまう。」と言われることがあります。 しかし、実際のところは、そこまで重い税金ではありません。税... -

すぐわかる!不動産評価額の調べ方
はじめに 今回は、財産評価において最も重要な不動産の評価について解説いたします。土地の評価単位、路線価方式と倍率方式、自用地としての評価だけでなく、借地権、貸宅地、貸家建付地の評価方法まで理解しておきましょう。 土地の評価単位 土地は、宅地... -

贈与税がかからない!4つの非課税制度
はじめに 高齢者が持つ資産を次世代へ承継することを促進し、わが国の経済成長を図ることを目的とする制度として、住宅取得資金、教育資金、結婚子育て資金に係る贈与税の非課税制度があります。今回は、これらの制度とともに、2,000万円の配偶者控除につ... -

相続時精算課税制度
はじめに 贈与税の計算には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体化するもので、次世代への資産承継を促進し、高齢者が持つ資産を活用して消費を増やすことで、わが国の経済成長を図ることを目的と... -

相続税とは?何に課されるの?誰が払うの?
はじめに 相続税とは、法律に基づいて、人の死亡を原因として財産が移転するときにかかる税金です。それでは、どのような財産に税金がかかり、誰が相続税を納めるのでしょうか。今回は、相続税の課税財産と納税義務者について解説いたします。 相続税の納... -

【まとめ】遺言の書き方・効力と遺留分
はじめに 遺言とは、人の死亡後の法律関係を定める意思表示のことです。遺言者が死亡したときに、その効力が発生します。満15歳以上で正常な意思能力がある人であれば、遺言を書くことができます。今回は、遺言の作成方法と遺留分について解説いたします。... -

相続人は誰?相続人になれる人を徹底解説!
はじめに 人が亡くなると、亡くなった人が持っていた財産を、特定の人が承継することになります。これを相続といいます。ここで、亡くなった人のことを被相続人、承継する人のことを相続人といいます。今回は、誰が相続人になるのか、、その相続人はどれだ... -

わかりやすい!不動産以外の財産の評価方法
はじめに 相続税法では、財産の評価原則として、「相続または遺贈により取得した財産の価額は、その財産の取得時における時価により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」という規定が設けられており、これ受けて国税庁は財産... -

相続税がゼロ円に!?配偶者税額控除のすべて!
はじめに 相続税の計算には、3つのステップがありました。第一ステップは課税価格の計算、第2ステップは相続税の総額の計算、第3ステップは、相続人それぞれが納付する税額の計算でした。今回は、第3ステップにおいて算出された相続税額から減算する「... -

会社の子供に継がせる親族内承継、社長の相続はここに注意したい
会社を子供に継がせることは、親族内承継と呼ばれます。子供に社長交代しすること、子供に株式を相続することが問題となります。その際の注意点を理解しておきましょう。 最大の課題は企業経営の承継 企業経営者は、社長であると同時に大株主です。大株主...
12